採用情報
インタビュー
「ずっとこの仕事を続けて行きたい」誰よりも山を愛する研究員
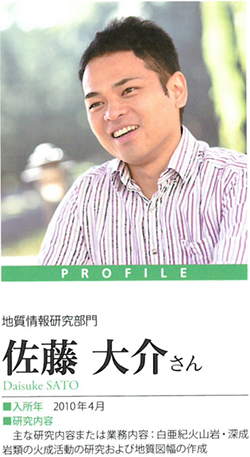 「3年間で200日くらい、島や山を歩いたりして。道ではないところも歩いて地層を見るので、地元の方よりたくさん歩いているかもしれません。歩いて確認した地層の情報を繋げて行って、線にして、さらに面にして地質図をつくっていくんです。」
「3年間で200日くらい、島や山を歩いたりして。道ではないところも歩いて地層を見るので、地元の方よりたくさん歩いているかもしれません。歩いて確認した地層の情報を繋げて行って、線にして、さらに面にして地質図をつくっていくんです。」
好きなことを仕事にしている人は、輝いている。佐藤さんは、まさにそれを感じる研究者だ。福岡県の山育ちで、山に抵抗はなかったという。卒業研究でのテーマも地質系のもので、修士卒業後に産総研に入所。研究内容は、白亜紀火山岩・深成岩類の火成活動の研究、そして地質図幅の作成である。最近、「播州赤穂」地域の地質図幅の成果をプレス発表したことで、大きな反響があった。
一度現地に足を運ぶと、大体15日間位は現地調査に入ったままで、長い時では3週間も。朝起きて陽が落ちるまで行い、宿に戻ってデータをまとめる作業の日々。そして現地の岩石を持ち帰って、顕微鏡観察など室内分析をする。「山は自由ですから。基本は自分一人なのでいいですね。」苦労を全く見せない佐藤さんは、大雨の時以外は調査に出るという。自分の中で地質学に基づいてポイント予測を立て、自分の足で歩いて確かめる。そして、また違う所を歩いて行くと繋がっていくので、自分の予想通りになっていくことが何より面白いと佐藤さん。
研究成果は、一般的には土木建築や不動産関係にも用いられている。例えば、この場所には断層がある、この土地は沖積層という新しい地層なので軟弱地盤である、などと読み解くことができる為だ。
この研究が難しいところは、白亜紀の岩石となると現在までとの間に1億年くらいあり、岩石が変質・風化したりするので、見た目が判別しにくくなる為に苦労がある。熱水によって変質したりしたものだと見極めること。見落とさず、同じ火山活動でできた岩石なのに違う岩石だと判断しないように気をつけているという。
現地調査は、専門の岩石が分布している地域を選んで行う。「イノシシや鹿もいますよ。まだ襲われたことはないですね」。と笑いながら語ってくれた佐藤さんの研究は、まさに自然と一体化した作業である。
「成果が世に出ることがやりがい。自分が出したもの反響があったり、周りの役に立ったり、活かしてもらえるようになったら嬉しいです。」 またどうしても調査区画が決まっていると、専門の白亜紀だけではない岩石も出てくる。そのため今後は、それも踏まえてしっかりと全体を見ることができ、その歴史を読み取れるようになりたいという佐藤さん。きっと何年経っても、今のように笑顔で地質のことを語ってくれるに違いない。
地球温暖化問題との出会いがあったから、今の自分がある
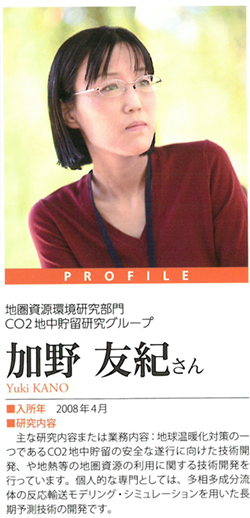 知らない街へ行くことが好きだという加野さんは、旅行と読書を愛する研究者。海外出張も増えてきて、ますます仕事が楽しくなってきているという。様々な国の人たちとの意見交換や、たくさんの情報収集ができることはもちろんのこと、「その国でしか味わえない空気が、全く違うんですよね」、そう自分が目にした世界を語ってくれた。
知らない街へ行くことが好きだという加野さんは、旅行と読書を愛する研究者。海外出張も増えてきて、ますます仕事が楽しくなってきているという。様々な国の人たちとの意見交換や、たくさんの情報収集ができることはもちろんのこと、「その国でしか味わえない空気が、全く違うんですよね」、そう自分が目にした世界を語ってくれた。
もともと環境問題に興味があった加野さんは、大学時代の授業で出会った地球温暖化に対するテーマに興味を持つようになった。学生時代と現在の研究内容では、海洋中の流動、貯留層の流動という違いはあるが、モデリング・シュミレーションの手法には共通するものがある。問題解決へのアプローチは、日々学びの途中だが、学生時代にその基礎を学ぶことができたという。
現在の彼女の研究は、地球温暖化対策の一つであるCO2地中貯留の安全な遂行に向けた技術開発と、地熱等の地圏資源の利用に関する技術開発である。
最も苦労するのは、地面の中というのはデータを取ること自体が難しい場所だということ。地中で起きている挙動を知るため、地面の上から弾性波を送ったり、比抵抗や自然電位、微重力を測ったり、場合によっては井戸を掘ってコア試料やデータを取ったりしている。広い範囲を高い精度で見るのは難しいことで、得られている限られたデータの中からいかに精度の高いデータを活かして、モデリングするかが大変なのだという。
「研究を進めていく上で、一人で考え込んでしまうとどうしようもなくなってしまう。産総研はせっかく幅広い専門の方がいるので、同じグループや部門をはじめ、別の領域の方にも積積極的に話を聞いています。それがとても刺激になるのです。」
産総研を選んだ理由は、研究員として自分が興味を持っているテーマを進められると思ったこと。また、大きな国のプロジェクトに加わることが出来て、さらに社会と直接関わる研究ができるということ。そして実際に今、自分の進めている研究が外に広がっていく実感があって嬉しいと、笑顔で答えてくれた加野さん。
研究所の採用は、博士号取得者の任期付きがほとんどだった中で、修士卒でパーマネントという採用プロセスをとっていたことも大きかった。安定した立場で腰を据えて研究が出来ることが魅力だったからだ。産総研では修士卒であっても、就職してから学位を取ることが出来る。実際に、加野さんも入所してから学位を取得しているのだ。
地中の流れは様々な要素が絡み合って成り立っていて、捉えづらい。だからこそ、「見える化」を進めていきたい。そして、今はモデリング・シュミレーションを専門に行っているが、今後は現地のフィールド試験なども積極的に参加して行き、実際の現象をしっかり捉えられるよう学んで行きたい、そう強く語ってくれた。
