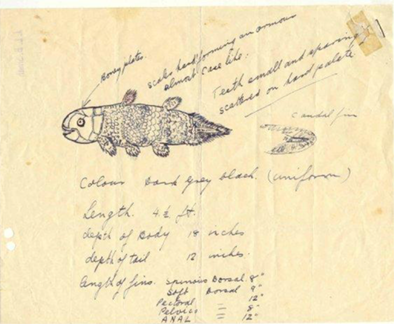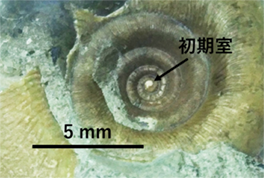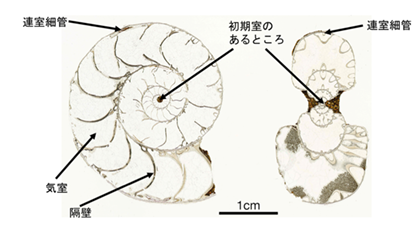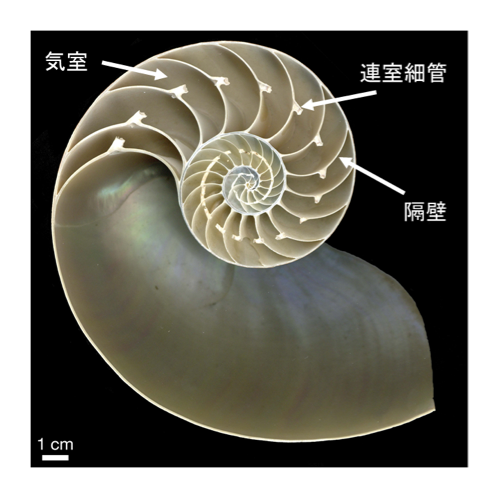ナウマンと地質調査所
産総研(産業技術総合研究所)の歩みは、1882年(明治15年)に国立の地質調査機関である地質調査所が設立されたことをもって始まります。この地質調査所の設立には、ドイツから来日した地質学者ナウマンが深くかかわっています。ここでは地質調査所が編纂した『地質調査所百年史』を参考にして、地質調査所ができるまでの経緯を簡単に記します。
地層の重なり具合や含まれる化石を調べることで地域の地質の成り立ち、ひいては地球の歴史を解明しようとする地質学という学問は19世紀のヨーロッパで発展し、その基礎が確立されました。そして、地質学の考え方や調査手法が石炭などの地下資源の開発に大いに役立つことから、世界の先進各国は本国に、場合によっては植民地にも地質調査機関を次々と設立していきました。同じころ日本では地下資源開発は重要であるものの、その調査手法が旧来のままであったため、江戸幕府や明治政府においては欧米から専門家を招き、地質や鉱山開発についての新しい知識や技術を習得する必要があると認識されていました。
幕末の1862年(文久2年)に江戸幕府が招へいしたアメリカ人地質学者のブレークとパンペリーは北海道の渡島(おしま)と後志(しりべし)地方の鉱床調査を行い、明治政府になってから1872年(明治5年)に招かれた同じくアメリカ人地質学者のライマンとマンローは北海道各地の地質調査を行いました。このときライマンが中心になって1876年(明治9年)にまとめた北海道の20万分の1地質図は、日本で最初の広域的な地質図として知られています。
1875年(明治8年)明治政府の招きで来日したドイツ人地質学者のナウマン(ハインリッヒ・エドムント・ナウマン)は、1876年(明治9年)に東京開成学校(現在の東京大学の前身)の教授に着任し、地質学の教育と研究を担当しました。1877年(明治10年)に東京大学が設立されるとナウマンは地質学教室の教授となり、その助教には後に地質調査所の初代所長となった和田維四郎(つなしろう)がいました。
ナウマンと和田は日本の地質の状態を明らかにするためには全国規模での地質調査を行うことがいかに重要であるかを説いて回り、国立の地質調査機関の設立を政府に建議しました。この建議は認められ、1878年(明治11年)に内務省に地質課が設置されました。ただ、地質課による地質調査は設備や資料も十分ではない中、容易には進まず、この状況を憂慮したナウマンは地質調査の組織、体制、計画などを具体的に記した長文の意見書を1879年(明治12年)に内務省に提出しました。意見書は採択され、20万分の1全国地質図幅調査事業の方針が初めて定められました。
地質調査を全国で展開していくため、庁舎や設備の整備、組織の新設、人員の充足が進められ、事業はようやく軌道に乗っていくようになりました。地質課では地質調査とともにさまざまな分析や試験も行っていて、業務の拡張に関する文書が当時の所管の農商務省に提出されました。この業務拡張案は認められ、1882年(明治15年)2月に地質調査所が公式に設立される運びとなりました。設立後の地質調査所ではナウマンが地質調査監督として地質調査事業の指揮をとりました。
さて東京大学地質学教室の教授時代、ナウマンは神奈川県横須賀で発掘されていたゾウの下あご化石を研究報告しました。その後1921年(大正10年)に静岡県の浜名湖北岸で見つかった同じ仲間のゾウ化石を京都帝国大学理学部助教授の槇山次郎が研究し、1924年(大正13年)にこれを新しい亜種であるとしてナウマンにちなんだ学名をつけました。このときに名付けられた学名により、それらゾウの和名はナウマンゾウと呼ばれることになりました。

出典:地質調査所百年史(地質調査所百年史編集委員会,1982年)
https://www.gsj.jp/information/gsj-history/history01/index.html
(2018年3月12日確認)